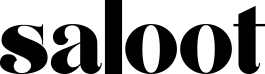目次
望まないのに、1人の人間の命を終わらせなくてはならない――。私は息子が生まれてすぐ、そんな現実に直面した。息子はダウン症という障がいをもって生まれてきた。「支援学校を卒業したあとは誰も守ってくれない」成長してからもことあるごとにそう言われ、息子の将来が不安で仕方がなかった。障がいを抱えた人が自分らしく生きていくために、何が必要なのだろうか。息子の親として、1人の社会人として、できることはあるのだろうか。これまでの経験を振り返りながら、あらためて考えてみた。
「健康に産んであげられなくてごめんね」”わが子が障がい者である”という現実に流した涙

「息子さんは、このままでは死んでしまいます。手術しますか」
長男を出産して間もない私に、医師はそう聞いた。すぐそばでは、生まれたばかりの息子が必死に呼吸をくり返している。わが子の生死の選択を迫られ、私と夫は動揺を隠せなかった。しかし、答えはもう決まっていた。
「お願いします」……その返事に医師はうなずき、すぐに手術の準備がはじまった。病名は「鎖肛(さこう)」。息子には生まれつき肛門がなかったため、人工的に肛門をつくる必要があったのだ。こうして彼は、生後数時間にして大きな試練と向き合うことになった。
手術は無事成功。術後の治療のため、息子はしばらくのあいだNICU(新生児特定集中治療室)で入院することになった。コットの中ですやすやと寝息を立てるわが子を見ると、私の胸は命が助かったという安堵感でいっぱいになった。同時に「あれ、この顔……」と思った。息子の目鼻立ちは、知り合いのダウン症のお子さんにとてもよく似ていたのだ。私は何気なく、夫にその感想を伝えてみた。
「あの子、障がい者なのかな」
「さあ、どうかな。でも、もしそうだったらどうする?」
あとから知ったことだが、夫は息子がダウン症であることをそのときすでに知っていたものの、私の心身への影響を考えて伝えなかったのだという。質問を質問で返されて、私は自分の心に聞いてみた。息子が障がい者だったら……、別に、それはそれで育てる。何度自問しても、答えは変わらなかった。
退院を間近に控えたある日、私たち夫婦は看護師さんから「退院後のケアや今後の生活のについて、先生からお話しがあります」と別部屋に案内された。ドアを開けると、座っていたのははじめて会う先生。しんと静まり返った部屋で、先生は私たちにこう告げた。
「お子さんは『ダウン症候群』です」
ある程度、予測していたことのはずだった。しかし実際に告知を受けてみると、私の目の前は真っ暗になった。なんで私だけ、どうしてこんな目に……。先生はダウン症について詳しく説明してくれたが、ショックのあまりまったく頭に入ってこなかった。私はあらためてNICUに行き、長男の顔を見つめた。それまで胸にしまい込んでいた思いが、堰を切ったようにあふれだしてきた。
「健康に産んであげられなくてごめんね」
涙があとからあとから、ほおをつたった。息子にも家族にも、申し訳ないという気持ちでいっぱいだった。わが子が障がい者であるという現実。それを受け入れるには、当時の私はまだまだ未熟だったのだ。希望に満ちていた世界は一瞬にして色を失い、自分だけが窓のない暗い部屋に取り残されてしまったようだった。
プロ並みのサポートで息子の可能性を伸ばしたい。前を向いた私が選んだ「31歳で看護学校」という道

しかし息子のそばで過ごす時間が長くなるにつれて、私の気持ちは前向きに変わっていった。息子は本当に愛らしく、掛け値なしに「誰とも比べなくていい」と思えるようになったからだ。彼が笑顔でいられるようにすることが、私の使命なのだと気づかされた。それからは息子の可能性を伸ばすために奔走する日々がはじまった。評判のいい療育施設があると聞けば見学に行き、育児相談に乗ってもらおうとダウン症協会にも入った。息子の将来を明るくするためなら、なんでもしたい――その一心だった。
特に心配だったのは、息子が社会に出たあとのことだった。「支援学校を卒業したあとは誰も守ってくれない。不自由なく社会生活を送るにはどうすればいいか、家庭で考えなければいけないよ」……障がいの当事者を含め、複数の人からアドバイスされた。たしかに、障がいがあると働き方の選択肢が少なくなりがちだ。一般企業に就職できる人はわずかなうえ、就職できても業務内容がくり返しの作業のみ、収入が著しく少ないという場合も少なくない。本人の希望とあわず、やりがいを失って長続きしない例もあると聞く。
一方で、ダウン症でもコミュニケーション能力や事務処理能力が高く、接客業務や管理業務を担当する人もいる。“ダウン症の書家”として知られる金澤翔子さんのように、類まれな芸術的才能を持つ人もいる。障がいを持っていても、本人の才能を花開かせることができれば、立派に自立して社会で生きていけるのだ。子どもが自立していくことは、すべての親の願いである。私と息子は「ファストフード店に就職し、大好きなハンバーガーを作る仕事がしたい」という夢を描いた。
夢を叶える方法を模索するうちに、息子の自立には親をはじめとする周囲のサポートが必要不可欠だということを知った。プロの方々に引けを取らないくらいの知識をもって、しっかりと息子をサポートしたい。そう考えた私は、31歳で看護学校に入学した。その後受験を経て准看護師の資格を取得。さらに3年間、病院で働きながら学校に通い、晴れて正看護師となった。看護師になるという選択は、私の人生観を大きく変えた。社会に出て働くことは、母ではなく1人の人間としての自分と向き合うきっかけにもなった。
障がいがあっても自分らしく生きられる。それがすべての人にとっての理想の社会

障がいの有無にかかわらず、すべての人が生きがいをもって暮らせる社会にするために、何ができるのか。私がたどり着いた答えは「コミュニティーづくり」だった。
人が充実した社会生活を送るためには「安全の欲求」と「社会的欲求」の2つが満たされなければならない。安全の欲求とは、経済的に安定し、住み心地のいい安全な住居で健康に暮らしたいという欲求。一方の社会的欲求とは、会社や家族といった集団に所属し、そのメンバーから認められたいという欲求だ。この2つの欲求が満たされるためには、誰もが安心して所属でき、その中で仕事も得られるコミュニティーが必要だと考えたのだ。
コミュニティーの具体例は、カフェの経営だ。ワークフローに工夫を施し、障がいのある人も問題なく接客や調理の仕事ができるようにする。さらに地元の農家と直接契約し、お店では新鮮でおいしい野菜をたっぷり使った料理を提供するとともに、農家での仕事口も確保する。障がい者のサポートには、農家を定年退職された方や、障がい者の家族が就くのもいいだろう。障がい者やその家族の自立支援とともに地元農家も応援できるという、一石二鳥のプランだと思っている。
それと同じくらい大事なのが、自己肯定感のベースづくりだ。特に重要なのが愛着形成が進む乳児期で、この時期に愛情をたくさん受けて育った子どもは、その後の人生を自信をもって歩める可能性が高いと言われている。社会生活のなかで自信を失いがちな障がい者にとっては、この時期の接し方がなおさら重要になってくる。
私は今、乳児院の看護師として、たくさんの乳児と接している。そのなかには障がいのある子もいれば、ない子もいる。息子と同じダウン症のお子さんをもち、障がいを受け入れられずにいるご両親にも出会う。さまざまな事情から、ご両親と離れて暮らすことになった子もいる。しかし親でなくても、周囲にいる大人が愛情をめいっぱい注ぐことはできるのだ。それが心の基盤となり、その子の社会的自立を助けてくれると信じている。今の経験から得た知識を多くの人に共有することで、すべての子どもが十分な愛情を受けて育てる社会をつくるための一歩にしたい。
社会には、いろいろな個性がひしめき合っている。背の高い人がいれば低い人もいるし、声が低い人もいれば高い人もいる。協調性のある人がいればわが道を行く人もいるし、社交的で活発な人がいれば穏やかで思慮深い人もいる。障がいの有無も、そういうありふれた個性のひとつなのだ。それが共通認識となってこそ、障がい者を含めたすべての人にとって生きやすい社会が実現できるのではないだろうか。近い将来には私が独自のコミュニティーをつくるまでもなく、すべての既存の組織や集団が障がい者にも開かれたものになっていてほしいと願うばかりだ。
著者紹介

樋口晴美 Harumi Higuchi ● 看護師。ダウン症をもつ長男の育児をきっかけに、31歳で看護学校に入学。2年で准看護師の資格を取得し、その後3年間病院で勤務。現在は乳児院の看護師として、子どもたちの心身の健康な成長をサポートしている。障がいの有無にかかわらず、すべての人が生きがいをもって暮らせる社会の実現を目指している。
編集協力/株式会社Tokyo Edit