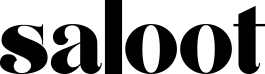目次
海外で暮らす日本人のために働きたい――。幼い頃からの夢を叶えるチャンスは、突如としてやってきた。文部科学省から「2015年度在外教育施設派遣教員募集」の通知を受け、応募したのだった。青森県、文部科学省の選考試験を通過し、派遣先は、マレーシア・クアラルンプール日本人学校となった。この記事ではこれから世界に羽ばたく女性たちへの一助として、その経験を振り返ってみたいと思う。
難関の選考、夫からの離婚宣告。クアラルンプール派遣への挑戦は波乱の幕開け
私は2015年(平成27年)4月、クアラルンプール日本人学校に派遣された。海外で暮らす日本人のために働くことは、学生時代からの夢。新卒で採用された中学校を学級崩壊を起こして辞職、2校目となる市立中学校からの派遣だった。子育てをしながら難関を突破するのは大変だったが、それだけに“2度目の正直”で夢を叶えられたときは感無量だった。
派遣が実現するまでの道のりは、想像以上に険しかった。まず立ちはだかったのは、家庭の事情だ。私には出願した当時、中学1年生と小学4年生の息子たちがいるうえ、夫からクアラルンプール行きを反対されていた。義母が体調を崩して入院中のさなか、夫は「そこまでして自分の夢を追うのか」「どうしても行くなら、帰ってきたら離婚だ」と譲らなかった。家ではほとんど口をきいてもらえず、家庭内はギスギスしていた。結局私は2人の息子を連れてのクアラルンプール行きを決意した。
派遣が決まってからは、ビザの申請や卒業証明書・戸籍謄本の発行、証明写真や現地への引越の手配、子どもの転校手続などで、寝る間を惜しんで渡航の準備をした。こんなときでも、毎日の仕事は待ってくれない。当時は中学3年生の学級担任だったので、専門教科である英語の授業に加えて三者面談や入学試験のサポート、卒業式の準備などもあり、目の回るような忙しさが続いた。精神的負担からか、次男の頭には円形脱毛が見られるようになった。幼い子どもたちを母親の人生に巻き込んでしまったようで、申し訳なさでいっぱいになった。
準備からして波乱づくしだったが、クアラルンプール行きを応援してくれる人もいた。入院中の義母だ。「好きなように生きなさい」「私はすぐに元気になるから、子どもたちは置いていけばいいよ」とまで言ってくれたのだ。いよいよマレーシアに発つ日には、ママ友や卒業させた元生徒たち20人近くが見送りに来てくれた。飛び上がるほど嬉しかったのを覚えている。
わかる喜び、学ぶ楽しさ。クアラルンプール日本人学校の児童たちが思い出させてくれた「教育の原点」

かくして3年間のクアラルンプール派遣生活がはじまった。クアラルンプール日本人学校は幼稚部、小学部、中学部という3つの学部からなり、私は小学部3年生の学級担任を任された。総生徒数1000人規模の大きな学校であるうえ、保護者の転勤などで生徒の入れ替わりが多いためか、誰にでも分け隔てなく接する寛容な子どもたちが多かった。一方で、保護者は小学校低学年のうちから英検を取得させるなど教育熱心な人が多く、教える側として背筋の伸びる思いだった。心配の種だった次男の円形脱毛はマレーシアに着いてもまだ残っていたが、空港の窓から大きなヤシの木を見つけて「ママ、オレさ、マレーシアが好きになりそう」と言ってくれたことは、私にとって大きな救いとなった。
学級担任として課題の添削や掲示物の準備などをこなしながら、専門教科である英語以外の教科も教えることになった。特に新鮮で楽しかったのは、理科の授業だった。虫眼鏡で黒い色画用紙を焦がしたり、ヒマワリの種を植えて育てたり、乾電池で豆電球を光らせたり。目を輝かせて実験に取り組む子どもたちを見て、教育の原点である「わかる喜び」「学ぶ楽しさ」にあらためて触れた気がした。色画用紙を焦がしすぎて部屋が焼き芋のようなニオイでいっぱいになったり、年じゅう高温のためヒマワリがまったく育たなかったりしたことも、今となってはいい思い出だ。

マレーシアに来て1年が経ったころ、2人の子どもたちを日本に帰国させることにした。中学3年への進級を控えていた長男は日本での入試準備があり、次男も日本にいたとき通っていた小学校に戻ることを選んだのだ。ようやくマレーシアでの暮らしに慣れてきた頃の帰国となったが、特に次男はこちらの食事になじめず日本を恋しがっているようだったので、今から考えてもベストな選択だったと思う。子どもたちが去ったあと、寂しくて涙したこともあった。しかし、自分のことだけをを考えていられる今は、貴重な時間でもある。残りの2年を公私ともに充実させようと気持ちを切り替えた。
しかし問題は私が帰国するまでの間、日本にいる家族が息子たちを見ていてくれるかどうかだ。「帰ってきたら離婚だ」とまで言われていた夫には、あれからほとんど連絡を取っていなかった。私は長男から夫に電話をしてもらうことにした。返事は「大歓迎」だった。私がそうであったのと同じように、彼も派遣によって距離ができたことで反省したり、歩み寄ろうと思う心が芽生えたのかもしれない。派遣期間中に退院していた義母の経過がよく、サポートが見込めそうだったことも功を奏した。
「どうしてうちの子はこのクラスなんですか?」最後の1年はクレーム最多の難関役職に

最後の年である3年目は学級担任を離れ、ECコーディネーターという役割を任された。ECとは「English Communication」の略称で、幼稚部、小学部、中学部の生徒たちに週2回の英語の授業を行うというものだ。勤務中に使えるのは、基本的に英語のみ。毎朝のミーティングはもちろん、職員会議の司会進行まで英語で行った。
最も不安だったのは、保護者対応だった。先述の通り、英語は保護者からの関心が高い教科である。そのぶんECコーディネーターには苦情も多いと評判で、実際に「どうしてうちの子はこのクラスなんですか?」「もっと上のクラスのレベルのはずです!」と連日のようにクレームが届いていた。このポストを任されたときは、不安を感じなかったと言えば嘘になる。
しかし、どうせなら前向きに楽しもうと気持ちを切り替えた。特に心がけたのは、積極的な情報発信と英語学習を楽しくするイベント企画だった。定期考査の試験範囲や日々の実践記録は、随時ホームページに掲載。「Choral Speaking Contest」と題した発表会を開催し、幼稚部から中学部3年生までの子どもたちに参加してもらったりもした。発表会では保護者の参観も行い好評を得るなど、8名のスタッフとともに充実した日々を過ごした。
多忙な日々を支えてくれたのが、いっしょに働いていたジェーンという女性だった。私は彼女に全幅の信頼を置き、ミーティングや司会進行時に使う英語の原稿も添削してもらっていた。当時60歳だったジェーンはたくさんの学校で主任を経験し、マネージメントに長けていた。いつも冷静で、元気がないときや自信が持てないときもけっして感情的にならない――それが彼女のマネジメントスタイルだった。そのおかげで、スタッフたちは無用な不安を抱かずに自分の仕事に集中できるのだ。
私が外国人スタッフとのコミュニケーションに悩んだときも、ジェーンは思いをストレートに伝えることの大切さを教えてくれた。育った国が違えば、行き違いが起きるのは当たり前だ。そんなときは「わかってくれて当たり前」と思わずに言葉を尽くし、互いに歩みよればいいのだと知った。スタッフたちが「あなたはマネジメントがきめ細やかね。いなくなったらどうしたらいいんだろう」と言ってくれるまでになれたのは、彼女のおかげだと感謝している。
ECコーディネーターの仕事に打ち込むうちに1年はあっという間に過ぎ、気がつけば帰国日が迫っていた。8名のスタッフたちとは、お互いの授業を参観しては悩みに耳を傾けるうちに絆は深まり、かけがえのない仲間になっていた。帰国する私のために、地元のレストランを貸し切って送別会を開いてくれたことは、本当にうれしかった。スタッフたちとは今でもSNSなどを通して連絡を取り合うなど、あたたかい交流が続いている。
◆ ◆ ◆
早いもので、マレーシアから帰国して3年が経った。時が経つほどに記憶があいまいになり、味わった感動や喜びはどうしても色褪せていく。しかし当時の経験から得たものが、私の中にしっかりと根付いているのを感じる。未知の物事と怖がらずに向き合い、冷静に判断する力。知識を教え込むのではなく、子どもたちと共に学び成長するという教育の姿勢。ずっと日本にいたら身につかなかった、異文化の知識。それらは私の生きる力となり、日々の生活をより豊かに、意義深いものにしてくれている。
人生を切り拓くのは、揺るがない信念だ――私はそう感じている。どんな困難に直面しても、自分の信じる道を一歩一歩、ただひたすらに歩みつづければ、道は拓けるのだ。女性の社会進出が叫ばれる現在でさえ、子どもの存在や家庭の事情を理由に夢をあきらめる優秀な女性たちはまだまだ多い。これほどもったいないことがあるだろうか。今は難しくても、もう少し先ならどうだろう。この方法はダメでも、違う方法なら夢が叶うかもしれない。女性たちにはそうやって、たくましくしなやかに夢を追い続けてほしいと思う。その道の先で、彼女たちが色とりどりの大輪の花を咲かせるのが楽しみだ。
著者紹介

福士 純佳 Sumika Fukushi ● 京都府生まれ、福井県育ち。大学進学時より母の故郷である青森県弘前市へ。2度の教員採用を経て2015年から3年間、文部科学省よりクアラルンプール日本人学校に派遣される。現在、市立中学校教諭。専門は英語科。ミセス・インターナショナル/ミズ・ファビュラス2021 インターナショナル部門 2nd Runner up(第3位)、アカデミック賞受賞。
編集協力/株式会社Tokyo Edit