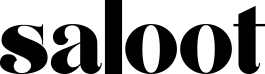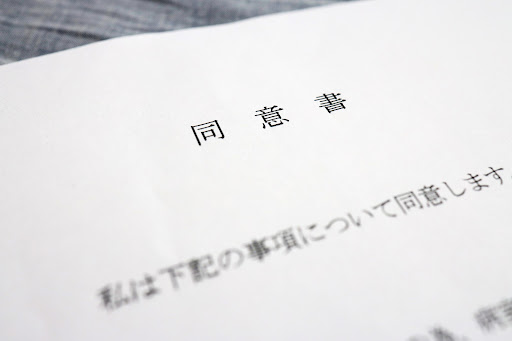
望まないのに、1人の人間の命を終わらせなくてはならない……。これは映画のなかの設定ではなく、今も世界じゅうで起きている現実の話だ。中絶――女性なら誰もが、当事者としてこの問題に直面するリスクを抱えている。実際に2018年の厚生労働省の発表によると、日本では年間約16万件もの中絶手術が行われている。これは離婚の年間件数である約20万件に迫る数値であり、中絶を経験する女性の多さを物語っている。女性たちはなぜ中絶を選択し、何に悩んでいるのか。みずからの経験をもとにその実態に迫り、社会問題としての中絶を解決する方法を模索する。
「産まない選択」をした私を襲った罪悪感

女性の社会進出が進む昨今だが、中絶をした女性への理解やケアはまだまだ不足している。中絶件数は離婚と変わらないほど多いのに、それをオープンにする人は少ない。日本では中絶を話すことはタブー、というような風潮があるからだ。そのため、中絶を経験したとしても表向きにはそれを隠し、何事もなかったかのように振舞う女性が多い。
かくいう私もその一人だった。当時私は30歳で、ビジネスパーソンとして脂が乗ってきている時期だった。大学卒業後勤めた会社では、上司や先輩方の後押しもあり早期に昇進するなど、成果も残していた。もともと出産願望が薄かったことも手伝い、プライベートよりも仕事優先の生活を送っていた。
妊娠がわかったのは、新規プロジェクトのメンバーを任され、ますます仕事に精を出したいと思っていた矢先のことだった。避妊をしたうえでの予期せぬ妊娠だったため、命を授かったよろこびよりも戸惑いが先にきた。今出産をして仕事を休んだら、私が任されたポストは誰かに取って代わられるだろう。産後、私が帰る場所が残されているかもわからない。せっかく授かった命なのだから、産んでから仕事のことを考えればいいという人もいるだろう。でも当時の私には、それが取り返しのつかない機会損失であるように思えた。結果として私は、中絶を選択した。
中絶を終えて、私はホッとしていた。自分の人生が返ってきた、これで今までどおり仕事ができると思った。しかし同時に、自分は許されないことをしたのだという罪悪感に苛まれることになった。自分が決めたことなのだからと、誰かに相談することもできなかった。時おりズキンとくる胸の痛みを日にち薬に託して、だましだまし日々を過ごしていた。中絶という決断も、それによって生まれた感情も、自分ひとりで引き受けなくてはならない。当時の私はそう考えていたのだ。
「女性が望んで中絶をした」ことにしたい社会

妊娠すれば女性はすぐに出産できる、とは限らない。子どもを育てる経済的余裕がない場合もあるし、相手が結婚や出産に同意しないこともある。私のように、仕事や学業を中断したくない人もいる。現段階で100%の避妊法はなく、出産の準備ができていないのに予期せぬ妊娠をしてしまう可能性は、誰にだってある。にもかかわらず、日本はいまだ、中絶を全面的に女性の責任とする価値観が蔓延っている。刑法で堕胎罪が規定されていることからも、これは明らかだ。
中絶を選択する女性への社会的圧力について、『中絶技術とリプロダクティブ・ライツ フェミニスト倫理の視点から(塚原久美)』の中では、次のように述べている。
「十分に(自分が望むような方法で)育てること」が実質的に不可能だと考えざるを得ない社会状況に置かれていると判断し、それゆえ「産まない」ことを選択したとすれば、それは彼女にとって「権利の行使」とは言えず、むしろ選択の強制にほかならないと考えるのである。そう考えることで、彼女が実質的に「選択権」を十全に遂行できるように、社会制度の変更を求めていく必要が生じる。
どんな場合でも、女性は中絶をすすんで選択するのではなく、なんらかの圧力によってやむを得ず選択しているのだと、塚原氏は言いたいのである。私もまったく同感だ。出産による学業やキャリアの中断を不安に感じさせる風潮が社会にあるとしたら、それ自体が圧力になりうる。中絶したくて性交する女性など、存在しない。社会からの目に見えない圧力によって、中絶せざるを得ない状況に追い込まれているのだ。それなのに中絶の責任を女性ひとりに押しつけ、なかば責めるような社会が実情である。
こうした圧力は、目に見えないからこそなおさら厄介だ。妊娠・出産をすると人事評価が不利になる、昇進が遅れるなどと明示されているわけではない。それでも、女性が妊娠や出産を機に出世コースを外されたという話は、後を絶たない。「マミートラック」という言葉が象徴するように、出産をした女性は仕事を続けられるとしても、昇進からは遠のく。こうした事実は厳然としてあるのに、国や企業は見て見ぬふりを続けている。
この状況を打開するためには、まず中絶をタブー視するのをやめることが必要なのではないだろうか。そして、女性を中絶に至らせる圧力があることを認めて「見える化」することだ。学生が予期せぬ妊娠をした場合は、休学だけでなくレポート提出による単位取得も認めるなど、代替手段の整備が求められる。仕事なら、休職によってこういうポストには就けなくなる、人事評価や待遇がこのように変わるということを、就業規則などに細かく記載するといった対応もときには必要だ。そうした規程は平等違反となるため、現実に制定されることはほとんどないが、制定したほうが皮肉にも実情にはあっている。
誰もが自由に生きられる、それこそが理想の社会
中絶によって女性が精神的なダメージを受けるのは、「女性は結婚して子どもを生むのが当然」という、社会からの無言のメッセージによるところも大きいと思う。戦後男女差別が撤廃され、女性も自由に生き方を選べるようになったはずだった。しかし、それはあくまでも建前。「女性は産む機械」という失言は極端だとしても、女性に生まれたなら結婚して授かった子どもを優先するのが好ましいという価値観は、やはり多数派だと思う。昨今の少子高齢化を大義名分にして、そういう価値観を押し付けてくる人もいるだろう。
しかし本来、限られた人生をどう生きるかを決められるのは、本人だけだ。その人自身が決めたミッションを果たすことこそが、何よりも大切なのではないだろうか。中絶をしても、結婚していなくても、子どもがいなくてもいい。そういう多様な価値観を許容し、それを支える制度が整っているのが、すべての人が生き生きと自分らしく輝ける社会だと思う。
中絶をした女性たちは、必ず別の何かを選択している。それはすでにいる子どもたちとの安定した生活かもしれないし、教養やキャリアかもしれない。中絶を選んだ結果、人生の選択肢が増えた人がいるかもしれないし、キャリアロスの回避によって生まれた企画や商品があるかもしれない。実際に私は、中絶を経験したあとに発展途上国で貧困に陥っている何万人もの女性たちを支援したり、被災地の雇用創出に汗をかく女性を知っている。彼女たちはひとつの命を終わらせたかもしれないが、その一方で別の何かに命を吹き込んでいる。
すべての女性が自由に人生を選び、生き生きと活躍する社会。それが実現してこそ、日本という国は本当の意味で未来に希望を持てるのではないだろうか。中絶を経験した女性は、今日からもう口をふさぐ必要はない。罪悪感に苛まれ、自分自身を責める必要もない。多くの人に向けて中絶を語ることこそが、ひとつの社会貢献なのだから。
著者紹介

小路 麻美 Asami Koji ● 大学卒業後、国税局に入局。プライベートでは中絶を経験する。その後出産を経験するも、出産後の働き方に疑問を感じて退職。現在はミャンマーのMJI社において、貧困層の女性の地位向上を目的としたマイクロファイナンス事業に携わる。自身の経験を生かし、中絶を経験した女性へのサポートをライフワークとしている。中絶した女性のケアや女性とキャリアの問題点等の発信を行っている。女性が自分の意思で人生を選択し、それぞれの可能性を最大限に生かせる社会の創出を目指している。
編集協力/株式会社Tokyo Edit